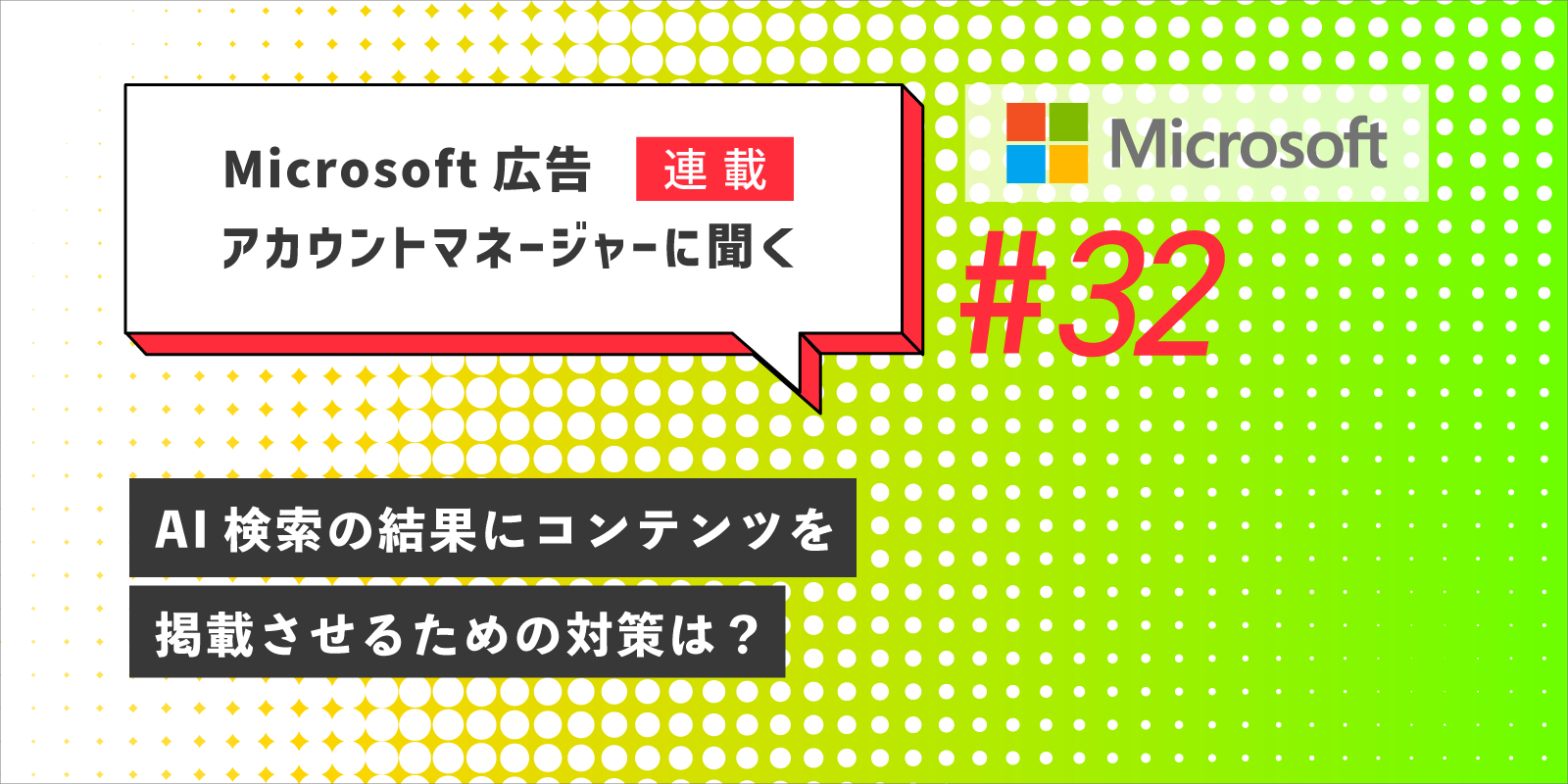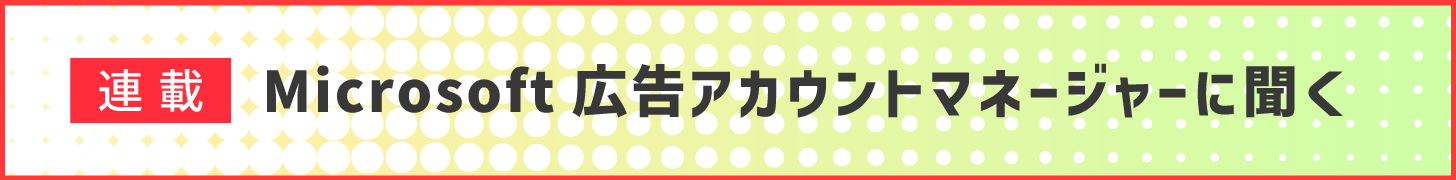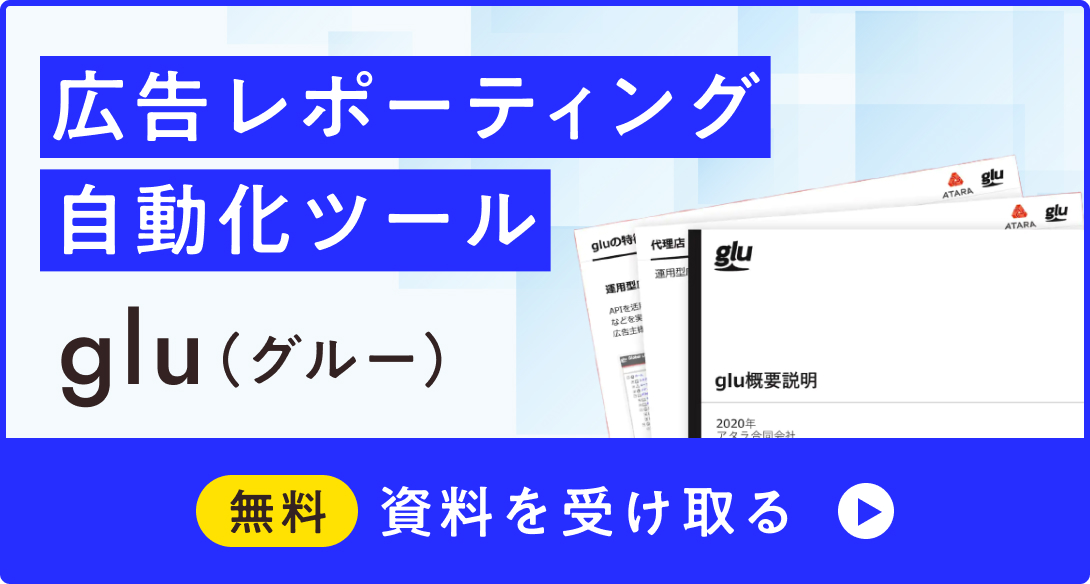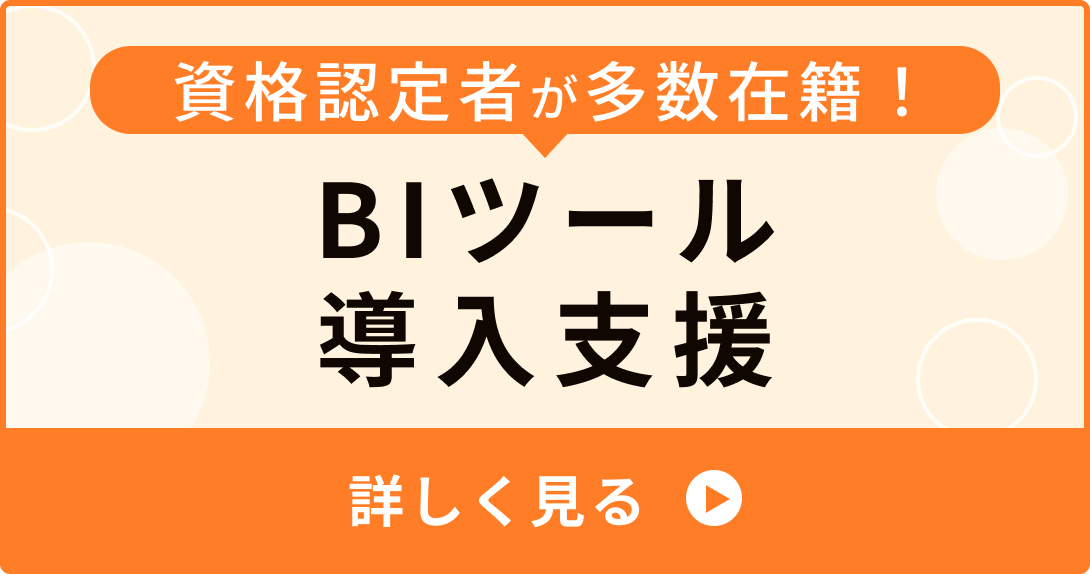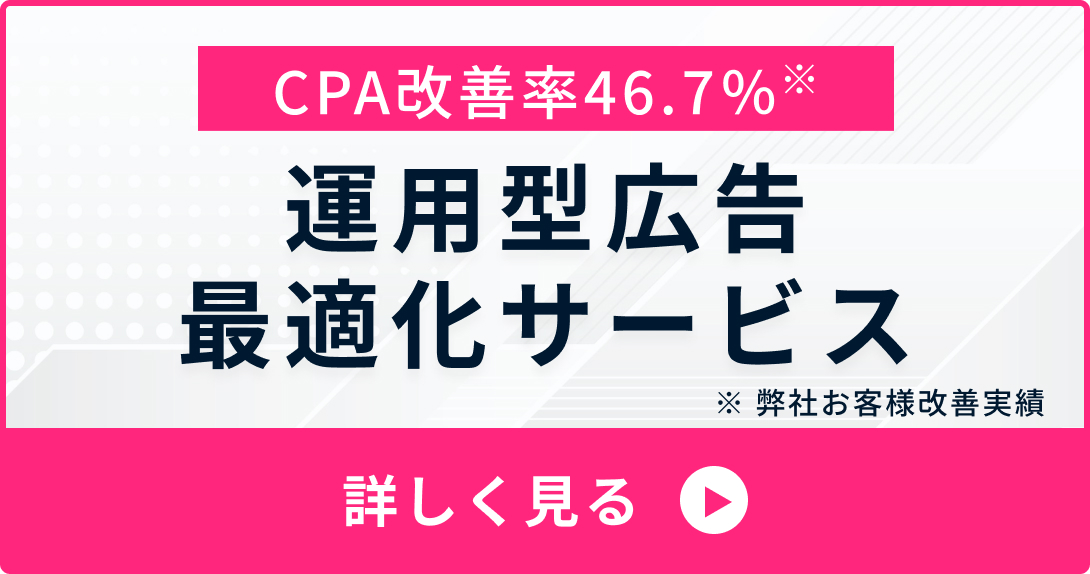Microsoft 広告について掘り下げる連載「Microsoft 広告アカウントマネージャーに聞く」。第32回となる今回は2025年10月8日に発表された「AI検索回答に選ばれる考え方・方法」についてお伝えします。
※参考リンク:
目次
急速に伸びるAI検索に対してマーケターがすべきこと
ここ数年、AI検索は非常に大きな成長を遂げています。2025年6月時点では、主要WebサイトにおけるAI参照数は前年比357%増、訪問数は11億3000万回に達しています(*)。AIO(AI Optimizationの略。AI最適化のこと)やGEO(Generative Engine Optimizationの略。生成エンジン最適化のこと)といった新たな言葉も生まれ、いわゆる「AI対策」への注目が高まっています。
出典:Optimizing Your Content for Inclusion in AI Search Answers | Microsoft Advertising
マーケターやSEO担当者がこれから取り組むべきことは、AIに“見つけられる”だけでなく“選ばれる”コンテンツを用意することです。では、AIに選ばれるためにはどのような対策をとればよいのでしょうか。ここでは、そのための考え方と手法を紹介します。
パーシングというプロセスを理解する
AIに選ばれるための対策の前に、まずはその仕組みを理解することが重要です。実は、AIは人間のように文章を隅から隅まで読んで理解しているわけではありません。ここで重要になるのが「パーシング(Parsing)」というプロセスです。AIはコンテンツを小さく分割し、使いやすい形にモジュール化します。モジュール化されたそれぞれの要素が評価(ランク付け)され、回答生成時に利用されます。
このとき、AIの回答は自社コンテンツだけで構成されるとは限りません。他社のコンテンツのモジュールと組み合わせながら、最適な回答を生成します。従って、自社コンテンツの一部をAIの回答に取り込んでもらうためには、パーシングを意識した構成と設計が求められます。つまり、AIが理解しやすく、モジュール化しやすい形で情報を整理・提示することが重要です。
ポイント1:有効な対策
AIに選ばれるためのコンテンツとして有効な方法は次のとおりです。
| ページタイトル | 検索意図に合った自然言語を使用して、コンテンツの内容を明確に要約する |
| 説明文 | AIとユーザーが文脈を理解するため、キーワードの詰め込みを避け、価値や結果を説明する |
| H1タグ | ページタイトルと一致し、その後の内容を明確に示す |
| タイトル/ディスクリプション/H1の一貫性 | 全ての整合性を保つことで、AIによる発見可能性と信頼性シグナルの両方が向上する |
| 見出し(H2とH3) | H2とH3は章のタイトルとなる。漠然とした見出しではなく「この食器洗い機が他のモデルよりも静かな理由」など、具体的な内容が分かる表現を使用する |
| Q&A形式を利用 | 直接的な質問に対し、明確な答えの形式をとる。AI生成の回答に組み込まれやすい |
| リスト・表形式を利用 | 箇条書きリスト、番号付き手順、比較表などは、ハウツー検索や機能比較でAIに使われやすい。またリストには箇条書きや番号をつけるリスト・表形式を利用 |
| 構造化マークアップ | 検索エンジンやAIシステムがコンテンツを理解するのに役立つコードの一種。AIに内容が伝わりやすくなる |
また文章を書く際には、次のポイントを押さえるとよいでしょう。
| 文脈を追加する | 例えば「静かな食器洗い機」ではなく「オープンコンセプトのキッチン向けに設計された42dBの食器洗い機」 |
| 同義語や関連語を使用する | 意味が強化され、AIが概念を結び付けやすくなる |
ポイント2:非推奨な表記・表現
AIに選ばれるために推奨されない、または注意すべき表現は次のとおりです。
| 長いテキスト | アイデアがぼけてAIがコンテンツを分割しづらくなる |
| 重要な回答をタブやメニューなどに隠す | 非表示コンテンツを読み込まない可能性がある |
| PDFにしない | 読み込まれない可能性がある。HTMLで書くようにする |
| 画像のみにしない | 読み込まれない可能性がある。代替テキスト追加、HTML表記とする |
| 句読点はシンプルに保つ | 解析を妨げる装飾的な矢印、記号は使用しない。また長文となる句読点のつけ方は避ける |
| 曖昧な表現は避ける | 「エコ」「革新的」など曖昧な表現は、同時に具体的な内容が入らない場合は使わない |
ポイント3:フィーチャードスニペット(強調スニペット)の対象となるようにする
コンテンツがフィーチャードスニペット(強調スニペット)の対象になるために有効な方法は次のとおりです。
| 簡潔な回答 | 質問に直接答える1~2文程度の回答 |
| 構造化されたフォーマット | リストや表、Q&Aといったブロック構造 |
| コンテンツ内がはっきり分かる見出し | その見出しの最初から最後までの意味を含む見出し |
| 自己完結的な文章 | 文脈(ページの他の部分)から切り離されて単独で抽出されても、それ自体で明確な意味を成す表現や文章 |
今回の発表についてのコメント(松井)
AIO、LLMO、GEOと新たな言い回しも増え、対策方法も信ぴょう性の高いものから噂レベルのものまでさまざま出ています。今回、AIと検索エンジンの開発者であるMicrosoftが施策レベルのAI対策を発表したことは、非常に有意義なことであると感じます。今後のAI対策として施策決定の指針となります。
とはいえ、AI対策についてはSEOをしっかり行うという土台の上で成り立つという原則には変わりがないという点もはっきりしたように思います。クローラビリティを意識する点・コンテンツの権威性や信頼性など質を重視する点・同時にコンテンツに一貫性を保つ点・ユーザーの読みやすさや使いやすさといったUI/UXを追求する点などはSEOと同様です。
AIとユーザー両方へ読みやすいコンテンツを提供しなければ、と頭を抱える方もいると思いますが、内容を俯瞰してみると基本的には今までどおりであり、そこまで構える必要はないように思います。AIはさらに進化をしていきますので、今後も注目していきたいと思います。